| 扇状地をつくろう! |
 |
「せんじょうち」・・・その名のとおり土地が扇子(せんす)の形になったもの。扇子とは,うちわと同じように風を送って涼しくするためのもの。折りたためて持ち運べるので便利。

扇子(せんす) |
川が山の中から平野に出てくるところで,川の幅は急に広くなる。
川幅が広がると,川の流れる速さが遅くなる。川の流速が遅くなると,川の水の中に混じっていた土や砂が川の底にたまるようになる。
川底に土砂がどんどん堆積してくと,川底がどんどん高くなっていく。あまりにも高くなると,川の流れはもっと低いところを見つけて流れを変える。
そうやって流路が変わるたびに,新しい流路のところでまた同じことが繰り返される。土砂の堆積と流路変更の繰り返しで,扇子状の土地が作られていく。
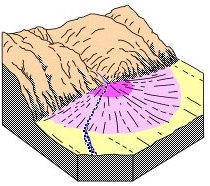 |
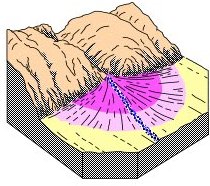 |
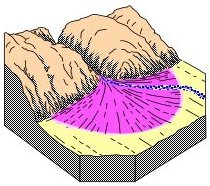 |
| 谷はまだ浅く扇状地は小さい |
山がけずれて土砂が運ばれる |
流れが左右に振れて扇状地ができた |
長野県松川村(まつかわむら)にある神戸原(ごうどはら)扇状地
芦間川のつくったきれいな扇子の形。開発が進んでいなく,扇頂から扇央にかけて針葉樹におおわれている。扇端は水田と集落が立地している。
これは,扇頂で地下にしみ込んだ水が,扇端でわき出してくるから。水が地下にしみ込むのは,扇状地が石や砂などの粒が大きめの土砂でできているから。
グーグルアースの画像

36.410000,137.830000
↑この数字をグーグルアースの画面左上の検索窓「ジャンプ」に貼り付け,高度を5kmくらいにする。
その他
・富山県の黒部川(くろべがわ)の河口にある黒部川扇状地
36.880000,137.515000 高度20kmくらいで見るのがよい
・北海道札幌市にある豊平川(とよひらがわ)扇状地
「札幌市豊平区」でジャンプ 高度は15km
| 材料 |
スコップ,水道とホースorじょうろ,砂場の砂 |
| 手順 |
1 校庭の砂場で山をつくる
2 山の上にホースまたはじょうろで水をかける
3 たくさんかける
4 山がけずれてくる
5 山のふもとに扇状地ができる |
| 注意 |
・よごれるので外靴とジャージを着用するほうがいい
・飽きたら砂山に水をどんどんかけちゃおう。どうなる?
ただし周りの人に水をかけちゃダメ |

砂場に山をつくる
|

ホースで水をかける
|

山がけずれてくる |

扇状地ができた |
|